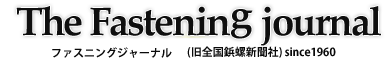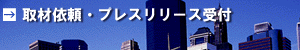村上泰賢氏の「わが国産業革命のはじまり」123 -日本産業革命の地・横須賀造船所
宥座ゆうざ之器
館林市の針生清司氏は銅司として板金加工を業とし「現代の名工」にも認定されている。たまたま館林で行われた筆者の講演を聴いて「父は横須賀造船所の工作学校で板金技術を身につけ技手補の資格を得て卒業した。若い頃あまり父の仕事を継ぐことに乗り気でなかった自分に『覚えておいて損はない』と伝えた。それがいつの間にか自分の仕事になっているが、その原点は小栗上野介の造船所建設による日本近代化構想にあったのか!」と感激したとのこと。
2012平成24年に東善寺に参拝し、小栗公のそばに置いてほしいと「宥座之器」を寄進してゆかれた。宥座の器とは手元に置くいましめの器、の意味。
針生氏は文献で知った「宥座之器」を制作することを思い立ち、調べると実際に出来上がって機能しているものは中国にも存在しないことを確かめた。それなら自分が作ろう、と試行錯誤の末に13年間かけて完成したという。
どのようなものか―使い方は四角いタライに水を入れ、柄杓で水をすくってツボに注ぐ。初めカラのときは少し傾いて吊られているツボは
「空っぽだと傾き、ほどよく水が入ると真っ直ぐに立ち、満ちるとひっくり返ってすべて失う」
孔子が弟子たちにこれを示し、人生におけるすべてのことにおいて、無理をすることや満ち足りることを戒め、中庸の徳、謙譲謙虚の徳の大切なことを教えている。「世の中に満ち足りて覆らないものがあろうか」と嘆じたという。仏教で説く「少欲知足」の生き方にも通じる。
「小栗上野介の横須賀造船所による近代化構想が、私の仕事につながっていた」と感激した針生氏のおかげで横須賀の職工学校の技術が現代に生きていることが確認できた。これまでに「宥座之器」を中国曲阜市孔子研究院、長崎孔子廟、岡山県旧閑谷学校、東京湯島聖堂、足利学校、行田教育文化センター、館林市内の学校や寺院などに寄贈している。折をみて現物を確認されたい。
本紙2671号(2024年12月27日付)掲載
バックナンバー
- 村上泰賢氏の「わが国産業革命のはじまり」123 -日本産業革命の地・横須賀造船所 2025.01.27 月曜日