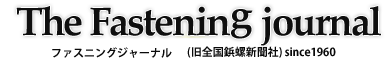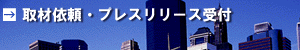村上泰賢氏の「わが国産業革命のはじまり」116 -日本産業革命の地・横須賀造船所
辰巳一(はじめ)・再渡仏し「松島」「厳島」建造
*小野雄司『造船大監 辰巳一』研成社参照
造船学応用学校に入学した辰巳たちはフランスの造船学の最高権威者であるルイ・エミール・ベルタン教授から指導を受けた。主な学習内容として造船学・蒸気機関学・熱力学・材料力学・工学・艦砲学・羅針盤操作・製図学(船体及び機関)・設計学(船体及び機関)などを学習し、3年間の修行を終えて1881明治13年12月卒業試験にも合格し、造船技師の資格を取得した。卒業証書にはわざわざ「…其の良好な態度、卓越した行動、仕事への熱心さを以て任務を果たし、指導教官の賞賛を得たことをここに証明する」と書かれてあるという。
1882明治14年12月、24歳で帰国し横須賀造船所御用掛となった。当時清国海軍は東洋地域の覇権を握ろうとドイツで建造の甲鉄艦「定遠」「鎮遠」艦(約7,000㌧)を始めとする海軍を充実していた。2艦で「遠くを鎮定」するという意味である。対抗して日本は甲鉄艦を貫通する砲を備えた軍艦製造を決定、明治19年にフランスからベルタンを招いて指導を受けることになった。
来日したベルタンは、後に「三景艦」と呼ばれる松島、厳島、橋立と三隻の軍艦(約4,200㌧)を設計し、辰巳はベルタンから再度の渡仏を指示されてツーロンで建造に当たることになった。三景艦の特徴は、船体をいくつかの隔壁で独立した区画を造り、一区画が被弾浸水しても他の区画の浮力で沈没を免れる構造としたこと。現在では当たり前の構造が、このとき始まっている。
軍艦を建造する膨大な量の設計書と計算書、注文契約書を作成し、さらに翻訳した仏語の書類も含め一年かけて仕上げ、ツーロンでは松島、厳島の二艦を建造し、橋立は横須賀で建造することになった。独りでツーロンへ派遣された辰巳は2艦の建造に6カ年尽力して仕上げた。基本的なこととして、設計図で用いる寸法では横須賀造船所建設工事以来、日本にフランス仕込みのメートル法が定着していたことが、この時現場でどれほど役立ったことだろう。
本紙2650号(2024年5月27日付)掲載
バックナンバー
- 村上泰賢氏の「わが国産業革命のはじまり」116 -日本産業革命の地・横須賀造船所 2024.06.27 木曜日