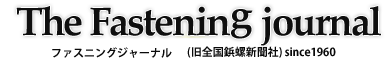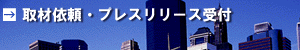村上泰賢氏の「わが国産業革命のはじまり」115 -日本産業革命の地・横須賀造船所
辰巳一(はじめ)・金沢から歩いて黌舎に入学
小野雄司『造船大監 辰巳一』研成社を参照
横須賀製鉄所で再開された黌舎で仏学を学ぶべく、辰巳一少年は金沢藩から選ばれた4名で、1870明治三年十月に東京に向かって旅立った。数え13歳、今の小6~中学1年生4人が、金沢から富山~越後~信州上田~上州高崎~武州の深谷~東京へ150里(600キロ)を歩いて16日間の旅をしている。藩の推薦があったから旅費をもらっていたにしろ、大人の付き添いなしに少年4人だけでワラジを履き、ほとんど歩いて旅を続けたのである。
元江戸の藩屋敷に着くと手配してもらって漁船を雇い、4日後の朝5時に江戸湾を南へ走って午後9時に横須賀に到着している。当時の漁船だからもちろんエンジンはない。風と櫓を漕いで進むしかないから、それくらいかかったが、歩かずにすむだけラクだったのだろう。
入黌はすぐに許されて、1878明治10年まで7年間もっぱら数学を中心に仏語で勉強した。その努力が実って、明治10年12月、辰巳はフランスのシェルブール軍港にある仏海軍造船学応用学校への官費留学生に選ばれ派遣された。
この造船学応用学校は、フランスの秀才が集まる理科系最高学府とされるエコル・ポリテクニック卒業生の中から、さらに特別優秀な学生が5、6名選ばれて入学できる学校。学生たちは入学しただけで仏国海軍造船造機武官として海軍大尉並みの官位が与えられる。だから、日本人留学生は横須賀の黌舎で教える仏人教授たちから、エコル・ポリテクニック卒業生と同等以上の数学の学力があると認められ、そこへの入学が許されたことになる。
一口に造船というが、船体工学と機関工学がかかわる。船の形状を研究し、商船であれば効率よく積み込む船体、軍艦であれば大きな大炮をバランスよく配置する設計、走力が出る船体や帆などを研究・改良・設計するのが船体工学。帆船から蒸気機関を使う時代に入ると、能率良く蒸気機関を使用するための機関工学が発達する。造船造機武官は2つの工学を兼ねていることになる。
本紙2647号(2024年4月27日付)掲載
バックナンバー
- 村上泰賢氏の「わが国産業革命のはじまり」115 -日本産業革命の地・横須賀造船所 2024.05.27 月曜日