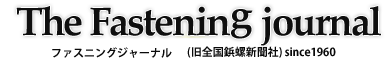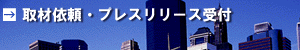ケヴィン山内の英語まめ知識
カラスは「黒」+「ス」
私が中学生の頃、受験英語で有名な雑誌社が出した辞書(?)になるべく楽しく早く英単語を憶えるコツが書いてあり、その中にcrow(烏)カラスは黒いからクローと憶えようとありました。他にnameはお前のナメーはとありました。たしか明治時代にdictionaryを「字引く書なり」と憶えようとしたのと同じですね。
ところで前者の著者は二つの単語とも英語と日本語が同じ語源から出ているとは考えても見なかったのではないでしょうか。今年の九月に大野進氏が「日本語の源流を求めて」を出版し、その中で日本語のルーツがインドのタミール語の影響を受けていると述べられています。又、レプチャ語と日本語の類似について発表した方が言語の専門学者でなかったので学界から無視された事があったと聞いています。以前の号で私が尊敬する歴史言語学者の川崎真治氏は上述のルーツをさらに辿るとシュメール(イラク)へ着くと発表されています。
さて大昔の人がその泣き声から出た音から英語ではcrowとなり、カラスは黒いので色が、そして鳥の名前には語尾に「ス」をつけるというアッシリア語(シュメール語も含まれる)から「黒+ス」がカラスになり日本へ入りました。カケス、ホトトギス、ウグイス、どうです少しは信用していただけますか? 学者の間では縄文時代に日本へ入って来たそうです。因みにインドで「アーダ」が日本では腕(ウデ)と枝(エダ)になったそうです。シャリは日本語で米ですが、シャリそのもので通じますね。
ある日本語学者は学生に語源を辿ってはいけないとわざわざプリントを配って止めさせているそうですがとても悲しいことです。少なくともアジア近隣のことばを勉強しなければ日本語の先生になってはいけないと思います。
本紙2007年11月27日付(2059号)掲載
バックナンバー
- カラスは「黒」+「ス」 2008.08.25 月曜日